 |
画像2 日当たりのよい谷脇の孤立木に着生したヒメノキシノブ。
撮影:(2002.3.24 県中部) |
 |
画像3 茎から疎らに出た葉は線形で,先が細くならないままに鈍頭となる。
葉の上面を縦に2分する1本の脈の左右に、小さな窪みが基部から先端まで
あるが、胞子嚢はその窪みではなく、上方の窪みの上下中間位置につく。
撮影:(2010.2.13 県北部) |
 |
|
 |
画像4 葉は長さ4ミリほどの明瞭な葉柄も含んで長さ3〜8cmほどになるが、変化が多い。
撮影:(2010.2.13 県北部) |
|
画像5 葉は下部から先端まで同じ幅で伸びて、急に狭くなって丸く尖る。尖り方にも変化が多い。
撮影:(2010.2.13 県北部) |
 |
|
 |
画像6 面は白身の強い淡緑色で、基部から先端に走る中央脈も色は同じで目立たない。
撮影:(2010.2.13 県北部) |
|
画像7 下面基部付近にある淡褐色の付属物は、不規則に出た未発達の胞子嚢群と思われる。
撮影:(2007.3.21 県北部) |
 |
画像8 胞子嚢群は葉の上部で脈の左右に平行してつくが、隣合わせではなくて
交互について、たいていは左右に5個づつだが多い時には8個づつにもなる。
撮影:(2004.11.13 県中部) |
 |
|
 |
画像9 ソーラス(胞子嚢群)は、直径1ミリほどでやや楕円状になる。苞膜はない。
撮影:(2010.2.13 県北部) |
|
画像10 ソーラスは、初め葉の上端についた後、だんだんと下方に向かってついてゆく。
撮影:(2010.2.13 県北部) |
 |
|
 |
| 画像11 根茎は茶褐色で太さ約1.5ミリ、樹上等を横に這う。撮影:(2004.11.13 県西部) |
|
画像12 根茎には披針形の鱗辺が圧着する。
撮影:(2010.2.13 県北部) |
 |
|
 |
| 画像13 岩場にコケと一緒に着生しているヒメノキシノブ。撮影:(2010.2.13 県北部) |
|
画像14 (参考) ノキシノブの葉。先端は尾状に長く伸びる。 撮影:(2010.2.16 県中部) |
|
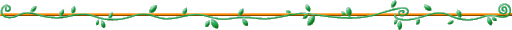 |
|
|
|
