 |
画像2 杉の木の天辺までも上るほど長く伸びて辺り一帯を覆い尽くす蔓の
総状花序は長いのは23cmにもなる葉柄の基部から立ち上がる。
撮影:(2010.8.29 県西部) |
 |
画像3 市街地を見下ろす高台の藪を覆い尽くしてさらに伸び続ける蔓は、
接地した節から発根すると親蔓から独立して個体を増やしてゆくらしい。
撮影:(2010.8.29 県央部) |
 |
|
 |
| 画像4 総状花序は高さ25cmほども長くなり、下から開花してゆく。花序の先は曲がっていることが多い。 撮影:(2005.9.5 県西部) |
|
画像5 紅紫色の花は長さ1.5cmほど、7ミリほどの花柄の先に5裂したガクがある。ガクも花柄も短毛がある。 撮影:(2005.9.5
県西部) |
 |
|
 |
画像6 翼弁より色が薄い旗弁は幅1.3cmほどで、基部には目立つ黄色い黄班がある。
撮影:(2005.9.5 県西部) |
|
画像7 花序最下の花はもうガクだけとなって、10本とも合生したオシベが見える。
撮影:(2005.9.5 県西部) |
 |
画像8 葉は大きな羽状の3小葉で、小葉は幅15cmにもなって3浅裂することが多い。
柔らかい葉は良く風に靡いて白っぽい下面が裏返しになって見えることが多く、
別名「裏見草」として平安期以降の和歌では恨みに通じる素材となっている。
撮影:(2010.8.29 県西部) |
 |
|
 |
画像9 葉の表面には白くて細い伏毛が全面に密生しているが、全体が白く見えるほどではない。
撮影:(2010.8.30 県央部) |
|
画像10 葉の下面には脈も含めて荒くて白い伏毛が密生し、全体が白っぽく見える。
撮影:(2010.8.30 県央部) |
 |
|
 |
| 画像11 出始めの新葉には上下面に黄褐色の毛がビロード状に密生する。 撮影:(2010.8.30 県央部) |
|
画像12 葉柄や小葉柄の基部は膨れて睡眠運動の機能を持つ葉枕の発達が顕著。 撮影:(2010.8.30 県央部) |
 |
|
 |
画像13 長い葉柄の基部には長さ1.7cmほどの舟形をした黄褐色毛の目立つ托葉がある。
撮影:(2010.8.30 県央部) |
|
画像14 小葉の基部には托葉よりは細い長さ8ミリほどの線状の小托葉がある。(左は托葉)
撮影:(2010.8.30 県央部) |
 |
|
 |
画像15 蔓には毛が多いが、色や形、量は成長度合いで変化し、古い茎では殆ど目立たなくなる。
撮影:(2010.8.30 県央部) |
|
画像16 高く立ち上がった蔓先は横に長く伸びて、黄褐色の毛が密生した逞しい先端部で絡まってゆく。
撮影:(2007.4.1 県央部) |
 |
|
 |
画像17 果実は長さ10cm近い扁平な豆果で、黄褐色の長剛毛に覆われている。
撮影:(2005.10.23 県中部) |
|
画像18 まだ小さく若い蔓なので、根は長さ1.6m。太い部分の長さは35cm、根の太さは最大部で直径2.3cm。撮影:(2010.8.31 県央部) |
クズ根の葛粉採取に関する畏友K君の話。
葛は、ボーイスカウトの隊長をしている時、国道10号線の山之口当たりの道路わきで、掘って採取し 砕いてさらした事があります。
ビール瓶ほどの大きさでしたが、堅くてなかなか包丁では切れず、なたで細かく切り刻み、試食したところ、えらく灰汁が強く、苦いものでしたが、食えない物ではありませんでした。それを降し金ですりおろし、一晩水にさらします。すると、上澄みは真っ黒で、底にまっ白い澱粉が大量に堆積します。いわゆる葛粉であり、葛餅の原料です。澱粉の含有量は相当なものです。 |
|
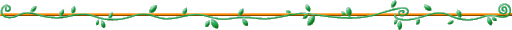 |
|
|
|
