 |
画像2 新しく出る根出葉は、小穂をつけた茎からやや離れた
場所から出る。(小穂基部の葉はもう枯れて消失した。)
撮影:(2016.4.14 西都市) |
 |
画像3 山地林内で小群落をつくった株、葉は長さ27cmもある。
(画像1は出たばかりの若葉だが長さ12cm、牧野図鑑
には、この種の葉の長さは12cm~32cmと書いてある)
撮影:(2010.8.26 諸塚村) |
 |
画像4 高さ約15cmの茎先の小穂で先端に雄花、下方に雌花がつく。
撮影:(2016.4.11 西都市) |
 |
|
 |
| 画像5 小穂の先に開花した雄花のオシベ、その下方で雌花が開花しかかっている。撮影:(2007.5.10 諸塚村) |
|
画像6 小穂先端に開花した雄花、3岐した長い花糸の先に葯が見える。
撮影:(2016.4.14 西都市) |
 |
|
 |
画像7 左下の雌花は淡紅色の3岐した柱頭が開きかかっている。
撮影:(2007.5.15 五ヶ瀬町) |
|
画像8 開花後、3個の柱頭が柔軟に曲がって受粉態勢となった雌花。
撮影:(2016.4.14 西都市) |
 |
画像9 葉は基部から徐々に広がって最大で3~4cmにもなり、また狭まって
披針形に細長く尖る。 左方に少し離れて有花茎が1本伸びている。
撮影:(2007.5.10 諸塚村) |
 |
|
 |
画像10 花の時期、古い葉は枯れて無く、新葉が伸びて広がる。
撮影:(2007.5.10 諸塚村) |
|
画像11 葉の上面。浅い縦溝があり無毛。葉縁には毛がない。
撮影:(2016.4.17 西都市) |
 |
|
 |
| 像12 葉の下面。殆ど無毛で記述すべき特徴は無い。撮影:(2016.4.17 西都市) |
|
画像13 葉の基部の葉鞘はやや赤味を帯びている。 撮影:(2016..4.17 西都市) |
 |
|
 |
画像14 有花茎の葉は退化して小さくて目立たず殆ど苞と同形。
撮影:(2016.4.17 西都市) |
|
画像15 花の時期の未熟な果胞で、高さ2ミリ、表面に毛は無い。
撮影:(2016.4.17 西都市) |
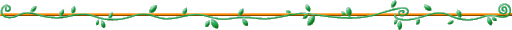 |
|
|
