 |
|
 |
| 画像2 葉腋から花軸を2〜3cmほど伸ばして平たい2枚貝のような苞葉をつけ、その中から二またに分れた上下2本の花柄を出して花をつけるので、上下二段になった花も多いが、上の花柄には花は一つしか咲かないので、二段花は開花初期だけの現象である。 |
|
画像3 昔から多くの名前があって帽子花もその一つだが、苞葉が烏帽子風の日本古来の帽子にも見えるし、また花弁を帽子のイメージとすれば烏帽子等の被り物とも見える。また西洋風の被り物とも見えるが、その場合には比較的新しい名前ということも考えられる。 |
 |
|
 |
| 画像4 中央のメシベ、その両側の長いオシベ2個、メシベの下方に見える黄色の葯を付けた少し長めのオシベ1個、底に見える黄色の葯を付けたオシベ3個、と、大きな青い花弁2個、その背後にもう1本の花柄と萎んだ花が見える。 |
|
画像5 苞葉の片側を取り除いて中を覗くと、下側花柄の花のすぐ下に蕾らしきものが見える。 |
 |
|
 |
| 画像6 画像5からさらに花弁も手前の1枚を取り除いてみたら、白い膜状の萼片3個、白い披針形をした3個目の下側花弁がよく見える。 |
|
画像7 苞葉の中の様子。上の黒っぽいのは花が終わって萎んでしまったもので、手で触ると色が付く。 |
 |
|
 |
| 画像8 葉表、無毛の卵状披針形で先は尖る。 |
|
画像9 葉裏、脈がよく見える。 |
 |
|
(露草)
うつりゆく色をば知らず言の葉の名さえあだなるつゆ草の花(山家集:西行)
ツユクサは露草で、朝早く咲いて午後には萎んでしまう花のように、はかなくさめやすいことの比喩として用いられたようで、万葉集では月草として多くの歌が詠まれている。
月草に衣は摺らむ朝露に濡れての後はうつろひぬとも(万葉集七:1351作者不詳)
月草は着き草の意で、花の色を衣に擦りつけて使っていたことから来ているらしいが、これで染めた色は直ぐに褪めてしまう性質を生かして、友禅の下絵などに利用されるようになり、大型の花弁を持つ変種のオオボウシバナが現在でも滋賀県辺りで栽培されているらしい。
(学名のCommelina)牧野図鑑の学名解説に
「17世紀のオランダにCommelinという名の植物学者が3名いて、JanとKasperの2名は著名だが、もう1人は業績を上げなかった。ツユクサの花弁3枚の内2枚は大きいが、1枚は不明瞭なのを例えてリンネが名付けた」とある。 |
| 画像10 葉の基部は毛のある鞘となって茎を抱く。二つ折りになった苞葉は下側の折れ目のところに毛がある。 |
|
鴨跖草(おうせきそう)という生薬名で、乾燥した全草を煎じて解熱や下痢止めに薬効があるそうだ。(薬草カラー大事典:伊澤一男 主婦の友社 1998) |
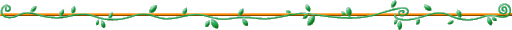 |
|
|
|
